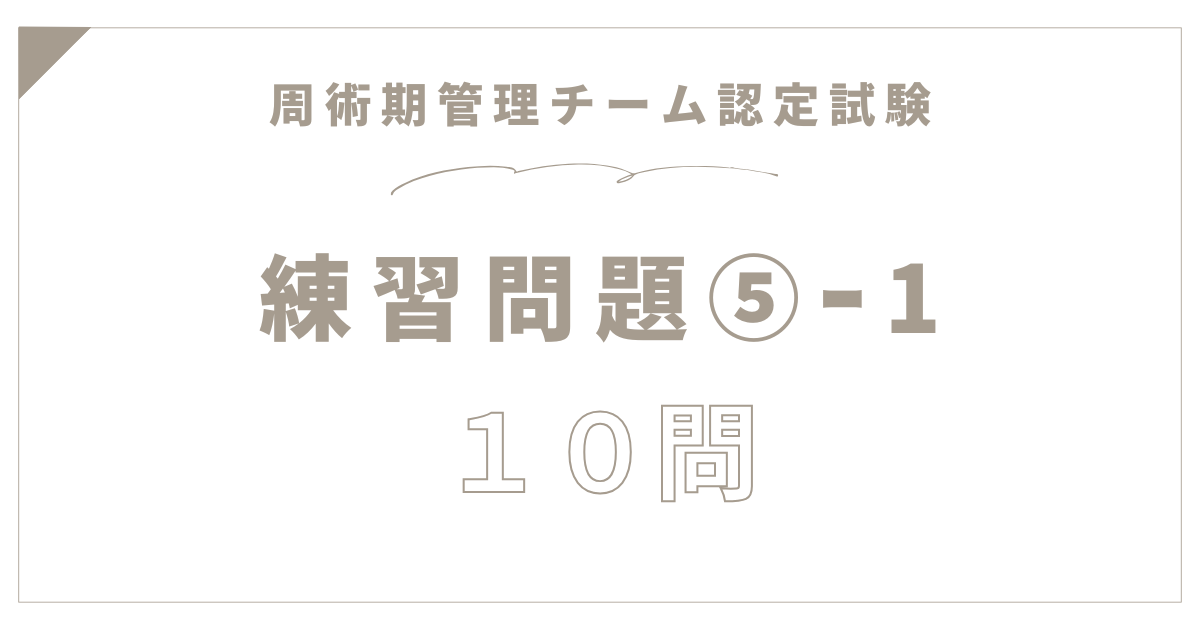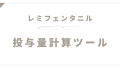周術期管理チーム認定試験の情報と、周術期管理チームテキスト第4版を参考にして作成しています。時代により解釈が変わり、正誤が変わる場合があります。
①レッドマン症候群
レッドマン症候群と関連する薬剤はどれか。1つ
a プロタミン
b ロクロニウム
c バンコマイシン
d クリンダマイシン
e フルルビプロフェン
答え
(c)
- 麻酔中のアナフィラキシーは,急激な血圧低下や換気障害で発症に気づくことが多く,迅速な対処(治療)が必要である。
| 症状 | 鑑別すべき病態 | 鑑別のポイント |
|---|---|---|
| 皮膚紅潮、発赤 | レッドマン症候群 | バンコマイシン急速投与 |
| 肥満細胞増多症 | 内因性ヒスタミン過剰。オピオイド,非ステロイド性抗炎症薬,バンコマイシン,筋弛緩薬などが誘因となることがある。 |
アナフィラキシーに対する対応プラクティカルガイドP18 4-6.発症時診断-鑑別診断 表4
周術期管理チーム認定試験2024年A参考
②局所麻酔薬中毒
非鎮静下における局所麻酔薬中毒の初期症状として正しいのはどれか。3つ
(1)多弁
(2)耳なり
(3)呼吸停止
(4)意識消失
(5)金属様の味覚
答え
(1)(2)(5)
- 1) 中枢神経系の症候
- 局所麻酔薬の中枢神経系への作用は、初期には大脳皮質の抑制系の遮断に伴う刺激症状から生じる。舌、口唇のしびれ、金属様の味覚、多弁、呂律困難、興奮、めまい、視力、聴力障害、ふらつき、痙攣などである。その後、興奮経路の遮断が生じると、抑制症状としての譫妄、意識消失、呼吸停止などが引き続く。同じく約 60%の症例においては、典型的な神経症状が緩徐に悪化する経過をとるが、直接に痙攣や心停止で発見されることもある。
- 2) 心血管系の症候
- 初期の神経症状に伴って、高血圧、頻脈、心室性期外収縮が生じる。その後、洞性徐脈、伝導障害、低血圧、循環虚脱、心静止などの抑制徴候が生じる。しかしながら、局所麻酔薬の直接の血管内への注入の場合などは、神経症候なしで循環虚脱を生じる。心電図上は、PR 延長、QRS 幅の増大が特徴的である。
金属様の味覚症状についてはプラクティカルガイドP5 B-1に情報が記載されています。
プラクティカルガイドも一通り目を通してください。
局所麻酔薬中毒への対応プラクティカルガイドP5 B-1 徴候、症状-中枢神経系の症候
関連情報:周術期管理チームテキスト第4版 P218,282,293,721
周術期管理チーム認定試験2024年A参考
③禁煙補助薬
禁煙補助薬について正しいのはどれか。1つ
a ニコチンパッチは創治癒を遅延させる。
b バレニクリンは心イベントを増加させない。
c ニコチンパッチは重篤な心イベントを増加させる。
d 手術までの待機期間が短い場合はバレニクリンによる治療を開始する。
e 手術までの待機期間が十分にある場合はニコチンパッチによる治療を開始する。
答え
(b)
- 禁煙補助薬;
- ニコチンパッチおよびニコチンガム:ニコチン置換療法(NRT)
- バレニクリン:ニコチンを含まない経口禁煙補助薬
- 禁煙補助薬として本邦で認可されている薬剤には,NRTで用いるニコチンパッチおよびニコチンガムと,経口薬のバレニクリンがあり,その使用によって禁煙率が高まる。周術期においてもNRTおよびバレニクリンは禁煙率を高め,術後もニコチン離脱症状を抑制でき,その後の禁煙持続率も高いと報告されている。
- 最近の大規模ランダム化比較試験で,バレニクリン,ニコチンパッチはいずれも,治療期間中および52週までの経過観察期間において心血管系の重篤なイベントのリスク増加がないことが確認されている。創治癒に関しても,ニコチンパッチは悪影響を及ぼさないことが示されている。
- バレニクリンは,服用開始後1週間は徐々に薬を増量し,この間は喫煙も継続し,8日目から禁煙する。手術日までの日数がある場合は,強力なオプションとなる。一方,NRTは使用と同時に禁煙する。術前の禁煙補助薬の選択にあたっては,これらの薬剤の使用法の特徴を踏まえ,手術までの期間を考慮して,期間が短い場合はNRTを選択すべきである。ニコチンパッチを選択した場合は,気管挿管時の心拍数を有意に増加させることが示されているので,虚血性心疾患患者では手術当日には除去すべきである。
周術期禁煙プラクティカルガイド4-5
周術期管理チーム認定試験2020年A参考
④吸入麻酔薬
吸入麻酔薬の MAC を変化させない因子はどれか。2つ
(1)性別
(2)年齢
(3)妊娠
(4)体温
(5)麻酔時間
答え
(1)(5)
- 最小肺胞内濃度(MAC)は皮膚切開を加えた時に50%のヒトで体動が認められない最小の吸入麻酔の肺胞濃度のことである。MACが高いと麻酔効果が弱い。
【表】MACを変化させる因子
| 上昇 | 高体温、甲状腺機能亢進、アルコール常用者 |
| 低下 | 年齢(加齢)、低体温、高度の低血圧、妊娠、低酸素血症、高・低二酸化炭素血症、 代謝性アシドーシス、オピオイド、ケタミン、アンフェタミンの長期投与、 化学伝達物質(レセルピン、メチルドパ、レボドパ、エフェドリン)、 コリンエステラーゼ阻害薬(常用量の10倍)、鎮静薬、筋弛緩薬、局所麻酔薬 |
| 変化なし | 麻酔時間、性別、代謝性アルカローシス、貧血、高血圧 |
周術期管理チームテキスト第4版P197
周術期管理チーム認定試験2024年A参考
⑤中心静脈路確保
中心静脈路確保について正しいのはどれか。1つ
a 内頚静脈穿刺は気胸のリスクがない。
b 高度無菌バリアプリコーションは必要ない。
c カテーテル抜去時には空気塞栓に注意する。
d ランドマーク法による穿刺が推奨されている。
e 消毒には 0.1% クロルヘキシジンアルコールを用いる。
答え
(c)
- 各中心静脈の短所・長所
- 鎖骨下静脈からの穿刺
- 術後管理がしやすい
- 重篤な合併症として気胸や血胸がある
- 内頚静脈からの穿刺
- 気胸を起こしにくいがないわけではない
- 頭頚部の手術以外での全身麻酔を受ける患者の第一選択
- PICCピック(末梢挿入型中心静脈カテーテル)。肘部皮静脈から挿入
- 気胸を起こしにくいのが利点である。(起きないことはない)
- 逆血、投与薬剤の残留、腕の曲げにより閉塞する可能性がある。
- 内頚静脈に迷入しやすい。
- 肘部皮静脈が穿刺に最も適している。
- カテーテル挿入時に頭部を穿刺側に保つ。
- 鎖骨下静脈からの穿刺
- 留置方法
- Seldinger法
- ガイドワイヤに沿ってカテーテルを前進させて留置する方法が一般的。
- ランドマーク法
- 解剖学的な目印を利用した中心静脈カニュレーションの方法
- 心肺蘇生のような緊急時などに有用な手段
- 超音波ガイド下穿刺法
- 内頚静脈(小児:内頚/大腿静脈)
- 合併症を減らすため、超音波ガイド下穿刺法が推奨されている。
- Seldinger法
- 合併症
- 動脈穿刺、血種、気胸、血胸、感染、ガイドワイヤによる不整脈、心膜貫通による心タンポナーデ、穿刺針による神経損傷
- 感染
- 血流感染の発生率を低下させるために、高度無菌バリアプリコーションが推奨されている。
- 消毒はポビドンヨードまたは1%クロルヘキシジンアルコールを用いる。
- 高度バリアプレコーション⇒帽子,マスク,無菌ガウンを着用し,清潔手袋を装着したうえで,広い穴空き覆布を用いてカテーテルを挿入すること
- 抜去時
- 穿刺部の穴から空気を吸い込んで空気塞栓を生じることがある
周術期管理チームテキスト第4版P243~
参考:安全な中心静脈カテーテル挿入・管理のためのプラクティカルガイド(2017)
周術期管理チーム認定試験2024年A参考
⑥術前の検査
術前の検査について正しいのはどれか。1つ
a D ダイマーは深部静脈血栓症の陽性適中率が高い。
b 血小板数が 10 万/μL では脊髄くも膜下麻酔は禁忌である。
c 1 秒量が 0.8 L の患者では周術期呼吸不全のリスクが高い。
d 空気吸入時の PaO2 が 90 mmHg 以下となる状態を呼吸不全と呼ぶ。
e 虚血性心疾患の場合,安静時心電図が正常であれば運動負荷試験を行う必要はない。
答え
(e)
| 検査値 | 特徴 |
|---|---|
| Dダイマー | 線溶の指標 DICや血栓症で増加 深部静脈血栓症の評価項目の一つ 陽性適中率(陽性のうち本当に疾患が存在する割合)が低いことに留意する必要がある |
| 血小板 | 肝障害、化学療法、出血性疾患などで減少 5万/μL未満の場合は、手術の内容により、血小板濃厚液の準備または、術前輸血を検討する。 血小板低下患者の硬膜外麻酔などの区域麻酔は硬膜外血腫のリスクが増大するため避けるべき。 脊髄くも膜下麻酔は5~8万/μL以上 硬膜外麻酔は8~10万/μL以上とする |
| 呼吸機能検査 | 1秒量が1.0L以下の場合は周術期呼吸不全のリスクが高い。 1秒率が70%未満を閉塞性換気障害 %肺活量が80%未満を拘束性換気障害 |
| 血液ガス分析 | 動脈血酸素分圧PaO2 が 60 mmHg 以下となる状態を呼吸不全とする |
| 心機能検査 | 運動負荷試験 →虚血性心疾患の場合、安静時心電図では異常所見が得られないことが多いため、運動負荷試験を行う。 |
テキストより該当箇所のみ抜粋
周術期管理チームテキスト第4版382~
周術期管理チーム認定試験2024年A参考
⑦希釈濃度・速度計算
体重 50 kg の患者にノルアドレナリン 1 アンプル(1 mg/1 mL)を生理食塩液49 mL で希釈した液を 15 mL/時で持続静脈内投与している。何 μg/kg/min で投与しているか。
a 0.01
b 0.05
c 0.1
d 0.5
e 1.0
答え
(c)
- 1000μg(1
mg)/50mL÷ 50kg × 15mL/時÷ 60分/時= 0.1 μg/kg/min
単位をかけたりかけたり割っていくと導き出せます。
ノルアドレナリンは1アンプル1mgと生理食塩液で計50mLとし、0.03μg/kg/min程度で開始する。(テキストより)
周術期管理チームテキスト第4版P99,221
周術期管理チーム認定試験2024年A参考
⑧気管挿管
気管支ファイバースコープを用いた気管挿管について正しいのはどれか。3つ
(1)食道挿管を起こさない。
(2)気道の損傷を起こさない。
(3)手技に訓練が必要である。
(4)頚椎不安定症例は良い適応である。
(5)ファイバーの外径と気管チューブの内径の差が小さいと成功率は上がる。
答え
(3)(4)(5)
気管支ファイバースコープは、唯一の柔軟な気道確保器具である。気道確保困難予測症例における意識下挿管、予期せぬ挿管不能・マスク換気不能時の気管支挿管に使用する。また、気道確保困難症例以外にも頚椎不安定症例においても使用される。
- 利点
- 気道の変形や病変を目で確認しながら、スコープ先端の角度を調節することにより、気管内に進めることができる。
- 欠点
- ファイバースコープを速やかに気管に挿入するには技術が必要である。普段から挿管困難出ない症例でその使用に慣れ、20~30秒以内に声門を確認できるように練習しておくべきである。
- チューブをファイバースコープ越しに進める際、チューブが披裂軟骨(ひれつなんこつ)などに当たり、しばしば挿入が困難となりうる。この頻度は、使用するサイズや形状によって大きく影響される。
- 気道閉塞や食道挿管などの重篤な合併症も起こることがある。
- ファイバー挿管の成功率を上げる方法
- 太い気管支ファイバースコープを用いる(例:外径5mm)
- 細い挿管チューブを用いる(例:内径6mm)
- スパイラルチューブを用いる
- ファイバーとチューブの組み合わせ
- ファイバーの外径と気管チューブの内径に差が大きい場合、ファイバーは気管内に進んでもチューブが声門にぶつかり、気管内に進まないことがある。
- ファイバーの外径と気管チューブの内径の差が小さいと成功率が上がる。
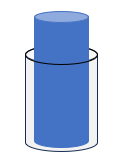
- 気管支ファイバースコープの盲点
- ファイバースコープではチューブの先端を確認できず、挿管自体は盲目的に行っている事実を知っておく必要がある。そのため、チューブ先端によって声門部の浮腫や気道の損傷を起こす危険性があるので頻回の挿管操作は避けるべきである。
周術期管理チームテキスト第4版P260~
周術期管理チーム認定試験2024A参考
⑨脳波
脳波について正しいのはどれか。3つ
(1)覚醒時の脳波はベータ波が主体である。
(2)深い睡眠時には周波数の低い波が主体となる。
(3)REM 睡眠時には筋肉は緩み,呼吸も不規則となる。
(4)Burst and suppression は麻酔深度が浅いことを意味する。
(5)皮質脳波モニターの種類によらず手術麻酔に適した値は 60~80 である。
答え
(1)(2)(3)
- (1)正解
- (2)正解
- (3)正解
- (4)麻酔濃度を上げていくと、脳波波形は一変し、平坦な脳波と大きな振幅の速い波が交互に出現する特異的なパターン(Burst and suppression)となる。さらに上げると平坦な波形になる。
- (5)40~60が適正値
- 皮質脳波モニター(BISモニター)
- BIS値 直近1分間から得られる推定値である。
- 平坦を0、最も覚醒を100とする。
- 40未満「深鎮静」、40~60「手術に適したレベル」、60~80「浅い鎮静」、80以上「覚醒」。
- BIS値と実際の鎮静度と乖離することがある。
- ノイズの混入、筋電図の混入、麻酔深度不十分時の疼痛、麻酔浅鎮静など。コラム1参照
周術期管理チームテキスト第4版P353~
周術期管理チーム認定試験2024年A参考
⑩前投薬
正しいのはどれか。2つ
(1)糖尿病では胃酸分泌が低下する。
(2)シメチジンは腎血流量を減少させる。
(3)制酸薬の使用目的は胃内容の減少である。
(4)メトクロプラミドの副作用に錐体外路症状がある。
(5)ファモチジンは腎機能低下があると作用持続時間が遷延する。
答え
(4)(5)
- (1)糖尿病では胃酸が亢進する。
- (2)シメチジンは肝血流を減少させる。
- (3)胃酸を中和することにより、誤嚥を生じた場合における肺障害の軽減が目的である。
- (4)正解
- (5)正解
周術期管理チームテキスト第4版P481~
周術期管理チーム認定試験2024年A参考