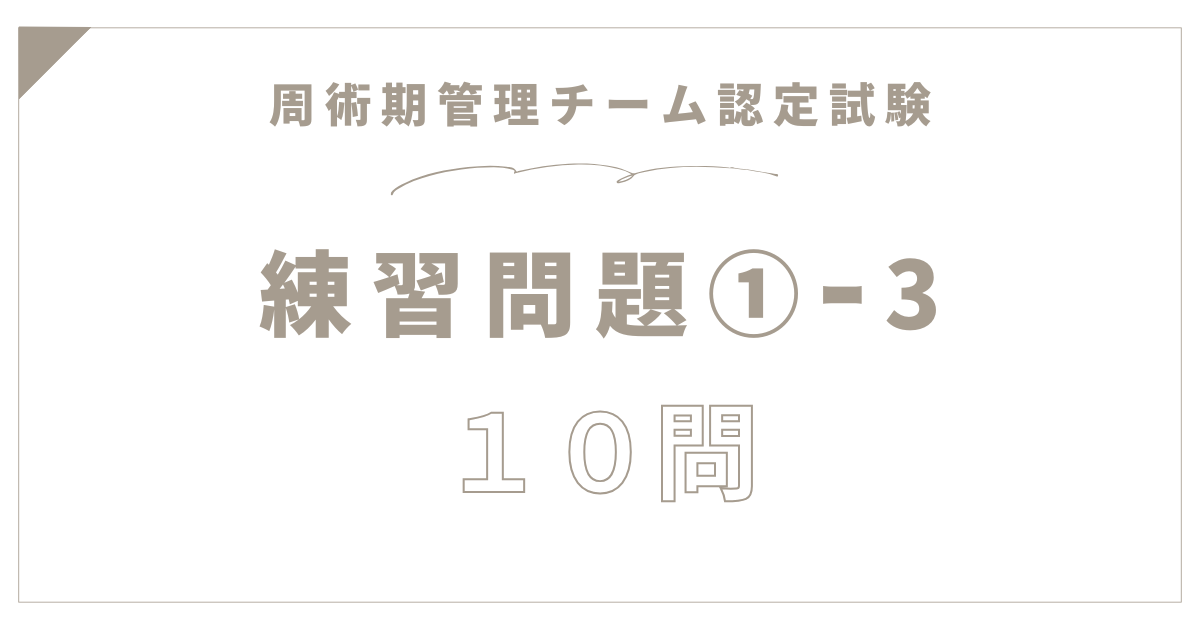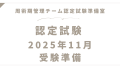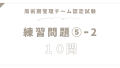周術期管理チーム認定試験の情報と、周術期管理チームテキスト第4版を参考にして作成しています。時代により解釈が変わり、正誤が変わる場合があります。
①手術体位を原因とする末梢神経障害について正しいのはどれか。2つ
(1)尺骨神経麻痺は男性に多い。
(2)橈骨神経麻痺の予後は不良である。
(3)砕石位では支脚台による脛骨神経麻痺に注意する。
(4)周術期末梢神経障害で最も多いのは腕神経叢麻痺である。
(5)フレーム支持台を用いる腹臥位手術では外側大腿皮神経麻痺に注意する。
答え
(1)(5)
- (1)正解(男性3:女性1)女性より肘部管が浅いため。
- (2)× 時間の経過とともに軽快し、予後はよい。
- (3)× 腓骨頭と台の間に総腓骨神経神経が挟まり麻痺が起こる。脛骨神経(けいこつしんけい)は、坐骨神経から分岐して下腿部を走行する神経。
- (4)× 周術期末梢神経障害(0.03%)で最も多いのは尺骨神経麻痺(28%)である。
- (5)正解
| 周術期末梢神経障害(0.03%) | 特徴 |
|---|---|
| 尺骨神経麻痺 | ・28%を占め周術期末梢神経障害の中で最も発生頻度が高い。 ・女性より肘部管が浅い男性に多い(男性3:女性1)。 ・まったく回復がみられず最終的に神経以降術が必要になる症例もある。 |
| 腕神経叢麻痺 (わんしんけいそうまひ) | ・尺骨神経麻痺に次いで多く周術期末梢神経障害の20%を占める。 |
| 橈骨神経麻痺 (とうこつしんけいまひ) | ・臨床症状は手関節の背屈障害である。 ・回復には数か月を要することがあるが、基本的には時間と共に軽快し、予後はよい。 |
| 総腓骨神経麻痺 | ・臨床症状は足関節と足趾が背屈できなくなる下垂足(かすいそく)と下腿の外側から足背ならびに第5趾背側にかけての感覚障害。 ・側臥位では手術台や膝を屈曲させたときのシーツのしわが下側の腓骨頭を圧迫する可能性がある。 ・砕石位では支脚台が膝の外側に当たると、腓骨頭と台の間に神経が挟まり麻痺が起こる。 ・回復は必ずしもよくなく、予後は不良の場合がある。 |
| 外側大腿皮神経麻痺 | ・臨床症状は大腿外側の知覚障害、しびれで、運動障害は合併しない。 ・多くの場合、数日~数か月で自然回復する。 |
| 坐骨神経麻痺 | ・周術期末梢神経障害の7%を占める。 ・臨床症状は大腿の伸展障害、下腿の屈曲障害、足関節の背屈・底屈障害、下腿外側と足全体の感覚障害である。 ・約半数の症例で運動麻痺が残存することがあり、予後は不良である。 |
周術期管理チームテキスト第4版P530~
周術期管理チーム認定試験2020年A参考
②次の抗凝固薬のうち ACT でモニタリングできるものはどれか。1つ
a ヘパリン
b ダルテパリン
c ダナパロイド
d エノキサパリン
e フォンダパリヌクス
答え
(a)
- a ヘパリン:APTT、ACT
- b ダルテパリン:抗Ⅹa活性(通常モニタリングしない)
- c ダナパロイド:抗Ⅹa活性(通常モニタリングしない)
- d エノキサパリン:抗Ⅹa活性(通常モニタリングしない)
- e フォンダパリヌクス:抗Ⅹa活性(通常モニタリングしない)
抗血小板薬や抗凝固薬でモニタリングできない内服薬は内服量の調節が簡便なメリットがあるが、周術期では、中止を検討したり、モニタリングできる薬剤に切り替えるなど、ガイドラインに従って対応する必要がある。
APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間Activated Partial Thromboplastin Time)
ACT(活性凝固時間Activated Clotting Time)
周術期管理チームテキスト第4版P506~ 抗血栓療法 P510 表3
周術期管理チーム認定試験2020年A参考
③術前に 7 日以上の休止期間が推奨されるのはどれか。3つ
(1)プラスグレル
(2)チクロピジン
(3)クロピドグレル
(4)シロスタゾール
(5)ジピリダモール
答え
(1)(2)(3)
- ○(1)プラスグレル 7~10日
- ○(2)チクロピジン 7~14日
- ○(3)クロピドグレル 7~10日
- ×(4)シロスタゾール 2~3日
- ×(5)ジピリダモール 1日
周術期管理チームテキスト第4版P508 表2
周術期管理チーム認定試験2020年A参考
④術前内服薬について正しいのはどれか。2つ
(1)喘息治療薬は手術当日も継続する。
(2)ワルファリンは手術当日も継続する。
(3)経口血糖降下薬は手術当日も継続する。
(4)カルシウム拮抗薬は手術当日に中止する。
(5)ステロイドの長期投与患者では周術期にステロイドカバーを考慮する。
答え
(1)(5)
- ○(1)喘息治療薬は手術当日も継続する。
- ×(2)ワルファリンは手術当日も継続する。→通常4日前
- ×(3)経口血糖降下薬は手術当日も継続する。→当日中断
- ×(4)カルシウム拮抗薬は手術当日に中止する。→当日でも服用
- ○(5)ステロイドの長期投与患者では周術期にステロイドカバーを考慮する。
周術期管理チームテキスト第4版P486~ 術前内服薬の継続あるいは中止の対処 表1
周術期管理チーム認定試験2020年A参考
⑤デスフルランについて正しいのはどれか。1つ
a MAC は 3%である。
b 気道刺激性はない。
c 交感神経抑制作用がある。
d セボフルランと比較して沸点が低い。
e セボフルランと比較して脂肪/ガス分配係数が大きい。
答え
(d)
- ×a MAC は 3%である。→通常6%前後
- ×b 気道刺激性はない。→ある。小児や末梢静脈路確保困難患者には不適当
- ×c 交感神経抑制作用がある。→刺激作用がある。小児や末梢静脈路確保困難患者には不適当
- ○d セボフルランと比較して沸点が低い。→28.8度(セボフルラン58.5度)
- ×e セボフルランと比較して脂肪/ガス分配係数が大きい。→他のハロゲン化吸入麻酔に比べて最も低い(デスフルラン0.42、セボフルラン0.64、イソフルラン1.4)
周術期管理チームテキスト第4版P196~ 吸入麻酔薬
周術期管理チーム認定試験2020年A参考
⑥オピオイドの投与法について誤っているのはどれか。1つ
a モルヒネの持続静脈投与
b フェンタニルの持続静脈投与
c レミフェンタニルの持続静脈投与
d フェンタニルの脊髄くも膜下腔投与
e レミフェンタニルの脊髄くも膜下腔投与
答え
(e)
- ○a モルヒネの持続静脈投与
- ○b フェンタニルの持続静脈投与
- ○c レミフェンタニルの持続静脈投与
- ○d フェンタニルの脊髄くも膜下腔投与
- ×e レミフェンタニルの脊髄くも膜下腔投与
→添加物としてグリシン(神経毒性)を含むため、硬膜外および脊髄くも膜下腔投与を行ってはならない。
周術期管理チームテキスト第4版P208~ 鎮痛薬
周術期管理チーム認定試験2020年A参考
⑦同種血輸血の免疫学的副作用はどれか。2つ
(1)発熱反応
(2)クエン酸中毒
(3)高カリウム血症
(4)輸血関連循環過負荷
(5)輸血関連急性肺障害
答え
(1)(5)
- ○(1)発熱反応
- ×(2)クエン酸中毒 → 非免疫学的副作用
- ×(3)高カリウム血症 → 非免疫学的副作用
- ×(4)輸血関連循環過負荷 → 非免疫学的副作用
- ○(5)輸血関連急性肺障害
血液製剤投与の副作用は非溶血性副作用と溶血性副作用に大別される。前者はさらに免疫学的副作用と非免疫学的副作用に分けられる。
| ○非溶血性副作用 ・非免疫学的副作用 | 発熱反応 (軽症)アレルギー反応 重症アレルギー反応(アナフィラキシー含む) 輸血関連急性肺障害(TRALI) 輸血後紫斑病(PTP) 血小板輸血不応状態 輸血後GVHD 輸血後免疫修飾(TRIM) |
| ○非溶血性副作用 ・非免疫学的副作用 | 輸血後感染症 クエン酸中毒 高カリウム血症 輸血関連循環過負荷(TACO) マイクロキメリズム 鉄過剰 |
| ○溶血性副作用 | 急性溶血性副作用(ABO不適合輸血、機械的溶血) 遅発性溶血性副作用(不規則抗体に由来する反応など) |
周術期管理チームテキスト第4版P578~ 表3
周術期管理チーム認定試験2020年A参考
⑧神経疾患患者の術前評価について正しいのはどれか。2つ
(1)パーキンソン病患者の一部では認知機能低下が認められる。
(2)Glasgow Coma Scale は意識状態を 1 から 300 の数字で表す。
(3)重症筋無力症患者ではベンゾジアゼピン系薬剤の前投薬を行う。
(4)T5 以上の脊髄損傷では急性期に治療抵抗性の徐脈・低血圧が生じる。
(5)筋萎縮性側索硬化症の患者では術前に胸部エックス線で肺炎を評価する。
答え
(4)(5)
- ×(1)パーキンソン病患者の一部では認知機能低下が認められる。P434 4変性疾患
- ×(2)Glasgow Coma Scale は意識状態を 1 から 300 の数字で表す。E1V1M1~E4V5M6
- ×(3)重症筋無力症患者ではベンゾジアゼピン系薬剤の前投薬を行う。
ベンゾジアゼピン系薬剤は筋弛緩作用を有するため、重症筋無力症の症状を悪化させるおそれがある - ○(4)T5 以上の脊髄損傷では急性期に治療抵抗性の徐脈・低血圧が生じる。P435
- ○(5)筋萎縮性側索硬化症の患者では術前に胸部エックス線で肺炎を評価する。P432 4呼吸
周術期管理チームテキスト第4版P431~
周術期管理チーム認定試験2020年A参考
⑨血液疾患患者の術前評価について誤っているのはどれか。1つ
a 慢性炎症性疾患では血小板数が増加する。
b 鉄欠乏性貧血では大球性低色素性貧血となる。
c 閉塞性無呼吸症候群では二次性赤血球増加症を認める。
d 一般的に外科手術には 5 万/μL 以上の血小板が必要である。
e 血友病 A では第 VIII 因子活性が低下しており,aPTT が延長する。
答え
(b)
- ○a 慢性炎症性疾患では血小板数が増加する。P438
- ×b 鉄欠乏性貧血では大球性低色素性貧血となる。P439 →小球性低色素性
- ○c 閉塞性無呼吸症候群では二次性赤血球増加症を認める。P436
- ○d 一般的に外科手術には 5 万/μL 以上の血小板が必要である。p437
- ○e 血友病 A では第 VIII 因子活性が低下しており,aPTT が延長する。P440表1
周術期管理チームテキスト第4版P436~
周術期管理チーム認定試験2020年A参考
⑩小児の術前評価について正しいのはどれか。3つ
(1)いびきの既往では扁桃肥大を疑う。
(2)出生後 1 か月の児に前投薬が必要である。
(3)乳児において環境因子では体温は上昇しない。
(4)術前の風邪症状では喉頭痙攣のリスクが増加する。
(5)静脈路確保の難易度を評価するために四肢を診察する。
答え
(1)(4)(5)
- ○(1)いびきの既往では扁桃肥大を疑う。P454 2身体所見a一般診察
- ×(2)出生後 1 か月の児に前投薬が必要である。P456 前投薬
- ×(3)乳児において環境因子では体温は上昇しない。
- ○(4)術前の風邪症状では喉頭痙攣のリスクが増加する。P454 2身体所見b感冒・上気道炎
- ○(5)静脈路確保の難易度を評価するために四肢を診察する。P454 2身体所見a一般診察
周術期管理チームテキスト第4版P452~
周術期管理チーム認定試験2020年A参考
★関連問題